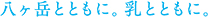魅力いっぱい八ヶ岳!
八ヶ岳の魅力を知れば、
八ヶ岳乳業のおいしさの秘密がみえてくる!
八ヶ岳連峰
本州のほぼ中央、長野県と山梨県に位置する「八ヶ岳連峰」。沢山の峰で形成された個性的な連峰で、国定公園にも指定されています。
しかし「八ヶ岳」という、ひとつの名前の山があるわけではありません。いくつもの山々の連なりの総称です。
名前の由来は「連なる山頂が八つ見える」説や「山の連なりがいくつもあるので沢山という意味の「八」から」など、諸説あります。
南北に広く、それによって色々な表情を見せる山々。北は原生林が生い茂り、南は八ヶ岳の主峰赤岳(標高2899m)を中心に雄大な山麓をなし、そこには多くの貴重な動植物や、豊富な湧水、火山地帯による温泉など、自然の魅力がいっぱいです。

八ヶ岳の動植物
○動物
-

ニホンカモシカ
偶蹄目ウシ科。体調105~112cm。全身の毛衣は白や灰褐色。草や木の葉、芽、樹皮、果実などを食べる。単独で生活をしているため、4頭以上の群れをで見かけるのはまれ。
-

ニホンリス
齧歯目リス科。体長16~22cm。腹面や尾の先端の毛は白い。夏季は、赤褐色。冬季は、灰褐色に体毛が生え変わる。おもにどんぐり、まつぼっくりなど木の実や若菜を食べる。
また、リスは昼行性のため、早朝に出会える可能性高い。
○野鳥
-

ウソ
スズメ目アトリエ科。体調15~16cm。頭の上と尾、翼は黒色。背の部分は灰青食。のど下がオレンジ色。くちばしが太い。八ヶ岳では、ポピュラーの鳥。11~5月によくみられる。主に、植物の種や木の実を食べ。春は、サクラ、ウメ、モモなどの花やつぼみをよく食べる、鳴き声は、フィーフィー。
-

アカゲラ
キツツキ目キツツキ科。体調20~24vm。黒、白、赤の3色からなる。主に昆虫、クモ、多足類を食べるが果実、種子なども食べる。鳴き声は、キョッキョッ。
主に、枯れ木の幹をくちばしでつついて、木の中の虫を採取したり、巣を作ります。森の中に響くけたたましい音は、この音です。
○植物
-

コイワカガミ
イワウメ科イワカガミ属の多年草。低山帯から高山帯まで幅広く分布する。名前の由来は、生育場所が岩場で、光沢のある葉を鏡に見立てたことから。
背丈は低く、花は淡紅食。花弁は5つにわかれ、先端は細かく避けている。花の開花時期は、春から夏。 -

ヤツガタケナズナ
アブラナ科イヌナズナ属の多年草。高さ20cm前後。
生息地は、八ヶ岳の湿った岩場にみられる。
花の開花時期は、7~8月。
自然遷移による減少が大変危惧されている。 -
八ヶ岳の名称がついている植物
ヤツガタケキンポウゲ(八ヶ岳金鳳花)、ヤツガタケナズナ(八ヶ岳薺)、ヤツガタケサクラ(八ヶ岳桜)、
ヤツガタケキスミレ(八ヶ岳黄菫)、ヤツガタケムグラ(八ヶ岳葎)、ヤツガタケアザミ(八ヶ岳莇)【八高嶺莇】、
ヤツガタケタンポポ(八ヶ岳蒲公英)、ヤツガタケイチゴツナギ(八ヶ岳苺繋)、ヤツガタケシノブ(八ヶ岳忍)、
ヤツガタケトウヒ(八ヶ岳唐檜)、ヤツガタケジンチョウゴケ(八ヶ岳沈丁苔)
上記、ほとんどのものが八ヶ岳が発見地となっています。
八ヶ岳の固有種と言えるのは八ヶ岳菫と八ケ岳金鳳花の2種です。
八ヶ岳エリア


-
富士見高原

八ヶ岳の南に位置し、四季それぞれ、季節ごとの景色が楽しめる、富士見高原リゾート。
スポーツ施設も充実し、冬はスキー、夏はテニスやパラグライダー、ゴルフ等が楽しめます。
また夏にリフトやカートで行くことができる展望エリアは、お子様ご年配の方でも気軽に楽しめます。
-
霧ヶ峰

八ヶ岳の中部に位置し、最高峰の車山1,925mを含め、ゆるやかな起伏が続く霧ヶ峰高原。
富士山や日本アルプス、八ヶ岳の山々の雄大な景色を楽しむことができます。
スキー場やグライダーの滑走などスポーツも盛ん。
また高原の涼しい気候で、橙色のレンゲツツジや黄色のニッコウキスゲなど、季節の高山植物が草原を彩ります。 -
白樺湖・女神湖

蓼科山からの水によって広大な湿原だったところに、人々の暮らしを支える農業用の溜め池としてつくられた白樺湖・女神湖。現在は美しい景観が自慢の観光スポットとなっています。
-
諏訪湖

信州一大きな湖である諏訪湖は、諏訪地方の人々の生活に溶け込み、温泉が楽しめる観光地としても知られ、季節を問わず観光客が訪れる場所です。湖畔を走るマラソン大会や、夏の大花火大会など楽しいイベントも沢山。
また、寅年と申年に行われる「御柱祭」は奇祭とも言われる大祭で「7年に一度」諏訪地方の全体が熱気に包まれます。
八ヶ岳と水
○八ヶ岳の水
山麓での豊富な降雪・降水は、地下に浸透し、湧水としてすばらしい水資源となっています。
八ヶ岳南麓にはこのような湧水がいくつか知られていますが、これらはあわせて昭和60年に環境庁が選定した「日本名水百選」に指定されています。
「三分一湧水」(さんぶいちゆうすい)
「三分一湧水」は、戦国の世に、下流の三方の村々に三分の一ずつ平等に配分する為、時の国主、武田信玄の命令により分水マスの中に三角柱が建てられたことが名前の由来です。
一日に約8,500トンもの豊かな水が湧き流れるといわれています。

「女取湧水」(めとりゆうすい)
八ヶ岳南麓では一番高いところにある「女取湧水」は、湧水量が一日約10,000トンともいわれ、女取川の水源でもあり、昔から現在にいたるまで生活用水・農業用水の水源として利用されています。
○高原と水と酪農
八ヶ岳山麓の恵み溢れる自然環境は、酪農に適した地として昭和28年農林省より全国にさきがけて「高度集約酪農地域第1号」の指定を受けました。以来酪農が営まれ、良質なおいしい原料乳の生産がつづけられています。
環境が牛に与える影響は非常に大きく、良質な牛乳の生産を続けるうえでも、最適な環境を整えることがすなわち美味しい牛乳を生むのです。
牛を飼育するうえで水は切っても切り離せません。
牛の水分補給は、一回に4~5リットルの水を約20秒で一気に飲み干すほどで、その一日の量は気温の差などもありますが100リットル以上に達することもあります。
牛は熱に弱い動物で、ストレスを溜め込み餌を食べなくなってしまうことがあります。
水を体熱の発散に使用するのはもちろんのこと、乳の成分は約87%が水で構成されているため、水なくして牛乳は搾れないのです。
雄大で冷涼な高原の環境と、清らかな水をたくさん飲んで育った健康な牛。
そんな牛から搾られた牛乳は格別なものとなります。